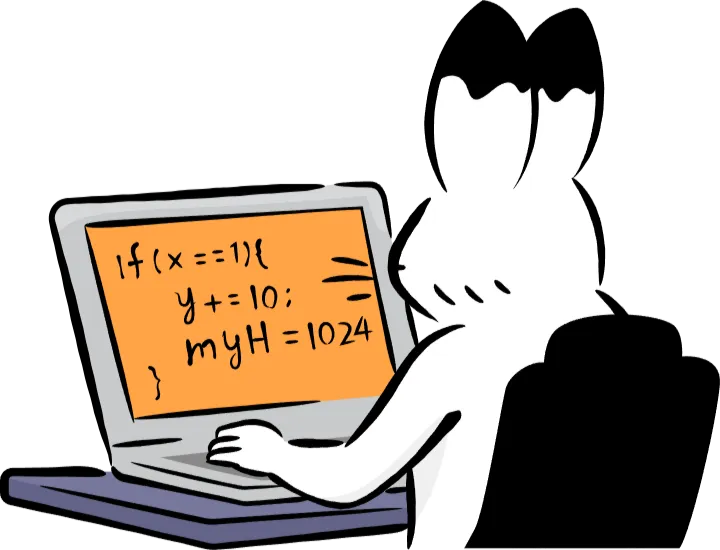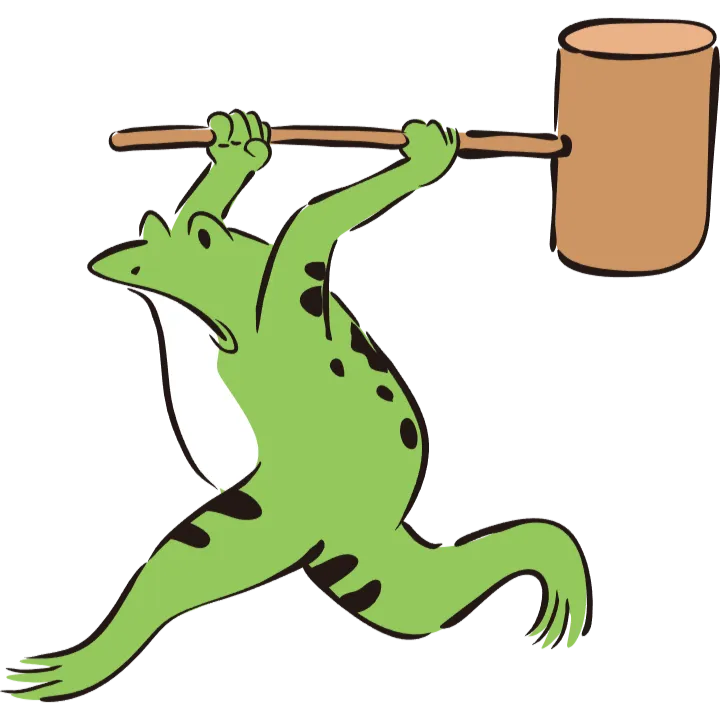在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
2024/04/04
目次
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
今回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」について入管業務専門の行政書士が解説します。ホワイトカラーの仕事として申請件数も多い在留資格ですが、申請に際し注意点もあるため、申請前に要件をしっかりと確認して許可を取れるようにしましょう。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動と定義されています。
在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」と一括りにされていますが、実際にはそれぞれ異なる在留資格であり、要件に適合していなければ申請しても許可は下りません。
在留資格該当性
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性は以下のとおりです。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
それぞれ解説していきます。
基準適合性
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準は以下のとおりです。
申請人はこの基準に適合していなければ、「技術・人文知識・国際業務」として日本へ入国することはできません。
《上陸基準省令の技術・人文知識・国際業務の下欄に掲げる活動》
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請に必要な書類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請に必要な書類は、申請区分と所属機関カテゴリーによって異なります。
それぞれの申請区分とカテゴリーで必要な書類は以下のとおりです。
認定申請(共通、カテゴリー1、2)
共通として下記の書類を提出します。また、カテゴリー1及び2については、その他の書類は原則不要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(指定の規格を満たした写真)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの)
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
認定申請(カテゴリー3)
カテゴリー3については上記に加え下記書類を提出します。
- 労働条件通知書等
- 雇用契約書等
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書等
- 登記事項証明書
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書等
- 直近の年度の決算文書の写し
認定申請(カテゴリー4)
カテゴリー4についてはさらに下記書類を提出します。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
変更申請(共通、カテゴリー1、2)
共通として下記の書類を提出します。また、カテゴリー1及び2については、その他の書類は原則不要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(指定の規格を満たした写真)
- パスポート及び在留カード
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
変更申請(カテゴリー3)
カテゴリー3については上記に加え下記書類を提出します。
- 労働条件通知書等
- 雇用契約書等
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書等
- 登記事項証明書
- 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書等
- 直近の年度の決算文書の写し
変更申請(カテゴリー4)
カテゴリー4についてはさらに下記書類を提出します。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
更新申請(共通、カテゴリー1、2)
共通として下記の書類を提出します。また、カテゴリー1及び2については、その他の書類は原則不要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(指定の規格を満たした写真)
- パスポート及び在留カード
- カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
- 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
更新申請(カテゴリー3)
カテゴリー3については上記に加え下記書類を提出します。
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
更新申請(カテゴリー4)
カテゴリー4についてはさらに下記書類を提出します。
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
- 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
申請における注意点
在留資格の許可を取得するためには、単に必要書類を揃えて申請するだけでは足りません。
前述した在留資格該当性や基準適合性について、申請人みずから立証や説明していかなければなりません。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請における注意点は以下のとおりです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性が認められるためには、その業務内容が「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」である必要があります。そのため、ホワイトカラーでない、いわゆる肉体労働や単純作業に従事する場合は、大学を卒業していても在留資格該当性がなく、許可を取得することはできません。
どのような業務が「自然科学」又は「人文科学」の「技術若しくは知識を要する」かについては、必ずしも明確な決まりがあるわけではありません。例えば、建設現場や工場が職場だからといっても無条件に在留資格が認められないわけではなく、申請人が工場内で工学の専門知識が必要な高度な製造業務に従事する場合、工場の生産性向上を図るため工場内の製造工程を見直すような業務に従事する場合は、在留資格該当性が認められます。
このような場合は、最低限必要な提出書類とは別に、採用理由書などを添付して、そこで詳しく説明しましょう。もちろん「在留資格該当性」や「基準適合性」を満たしているかどうかについても詳細に記載しなければなりません。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」はホワイトカラーが行う職種の多くをカバーしており、申請件数自体も他の資格に比べて多い資格です。しかしこの「技術・人文知識・国際業務」の資格でありながら、肉体労働や単純作業として雇用している企業も一定数あります。もちろんこれは不法就労に当たりますが、それらの企業は在留資格についてよく知らずに外国人を雇用してしまっているケースがほとんどです。外国人を雇用する以上は、入管法や不法就労、不法入国について一定の知識を必要とします。しかし、日々の業務や会社経営で忙しい場合は、入管法に詳しい行政書士などの専門家のサポートを受け、適正な外国人雇用を実現させましょう。
----------------------------------------------------------------------
行政書士堀井タヰガ事務所
住所 : 神奈川県相模原市緑区橋本3-27-6
S&Yビル4F
電話番号 : 050-6882-7467
相模原で在留資格の相談
----------------------------------------------------------------------